ホーチミン市の伝統的な市場は、少しずつ過去のものになりつつある。市場では、年を取った商人たちが屋台のそばに座り、にぎやかで慌ただしい現代の中で、記憶の炎を静かに守り続けている。
) (C) thanhnien |
) (C) thanhnien |
) (C) thanhnien |
タンディン市場(cho Tan Dinh)、バンコー市場(cho Ban Co)、ホアフン市場(cho Hoa Hung)、ホーティキー市場(cho Ho Thi Ky)など、ホーチミン市の多くの市場が、半世紀近く前から存在している。
多くの市場はひどく老朽化し、屋根は雨漏りし、壁は剥がれ、床は湿っている。「改修するか、撤去するか、保存するか」という問題は、長らく議論が続いている。方針が定まらない中でも、商人たちは毎日黙々と市場で過ごしている。
かつて、伝統的な市場といえば朝が最もにぎわう場所だった。人々はひしめき合って売り買いし、呼び声に値切りの声が交じり合う。その声は、街に流れる大衆音楽のようだった。市場は、何万もの家庭の食生活を支えるだけでなく、都市のアイデンティティの創造にも貢献してきた。
しかし、2000年代以降になると、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、オンラインショップが登場し、多くの伝統的な市場は徐々に勢いを失っていった。若者はかごを持って市場に出かける代わりに、「クリック」で買い物をする。売り手は座りっぱなしで疲れ果て、買い手はまばら、そんな状況だ。
そんな中でも、懸命に市場を守り続ける商人たちがいる。利益のためではなく、習慣だから、思い出だから、そして、市場が人生の一部だからだ。
旧8区(現在のビンドン街区)に古くからあるニティエンドゥオン市場(cho Nhi Thien Duong)は、地元の労働者の生活と密接に結びついている。ここでは、小さな天秤棒のおこわ売り、昔ながらの靴売り、何十年も続く野菜売りと、市場とともに生きる人々が、市場の記憶を静かに守り続けている。
毎日午前2時過ぎになると、グエン・ティ・ベー・ナムさん(女性・57歳)の狭い台所に火がともる。前日の午後に丁寧に洗い、水に浸しておいたもち米の入った鍋を練炭ストーブに置いて、おこわを炊く。そばでは夫が火を起こし、豆を洗い、ココナッツを削る。
ナムさんは、「この仕事をしてもう長いので、すっかり身体に染み付いています。起きておこわを炊かないと落ち着かなくて、おちおち寝てもいられません」と、頬を伝う汗をぬぐいながら笑う。
午前6時ごろになると、湯気を上げるおこわを載せた天秤棒を担いで、市場に向かう。小さな角の定位置に天秤棒を置くと、馴染みの出勤前の人や生徒、工場労働者などが集まってくる。おこわの香りに緑豆や削ったココナッツ、炒ったピーナッツの香りが混ざり合い、通り過ぎる人の足を止める。




)

 免責事項
免責事項
)

)
)
)
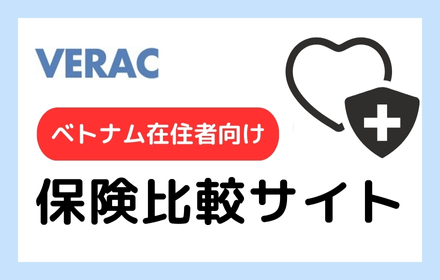
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)