この小さな野菜の屋台は、アインさんにとって生計を立てるためのものというだけでなく、人生そのものでもある。1束の野菜、1kgの玉ネギやパクチーには、苦しかった日々、忙しく立ち働いたテト(旧正月)の時期、そして雨の日も炎天下の日も家族の食べるものを心配した年月の記憶が詰まっている。
) (C) thanhnien |
) (C) thanhnien |
「市場をやめたら、きっと私は生きていけないでしょう。ここに来ない日があると、落ち着かなくて、何かが足りない気がするんです」。聞き慣れた呼び声と笑い声、そして朝日が差して徐々に明るくなっていく市場を見渡しながら、アインさんは語る。
アインさんの2人の子どもは、すでにある程度自立している。それでもアインさんは、引退は考えていない。「この仕事は、何十年も私と家族を養ってくれました。だから、自分に『まだ頑張らないと』と言い聞かせています。市場がある限り、私はここにいます」と話すアインさん。声を落としながらも、その目には静かな決意が宿っている。
今のバンコー市場は、昔とは違う。市場の周りにはコンビニエンスストアやスーパーマーケットが立ち並び、若者が市場に足を運ぶことも少なくなっている。「今どきの子は、急ぎで少しの野菜が要るような場合でもない限り、市場には来ません。あとはスーパーに行ったほうが便利ですから」とアインさんはため息をつく。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行期には、市場がまるで「息を止めた」かのような日々だった。売り手も買い手もほとんどおらず、かろうじて人の声が途切れ途切れに聞こえるだけだった。
アインさんは「新型コロナのときの市場は、本当に死んだみたいでした。商品はしおれ、人は借金を心配しながら家に閉じこもるだけ。今もまだ、あのときの借金を少しずつ返している人がたくさんいるんです」と、ゆっくりと話す。
それでもアインさんは、毎日市場に立つ。「私がまだこの市場にいるのは、学校に通っている孫たちのためです。家族の生活がこの野菜の屋台にかかっているから。それに、ここには『昔のサイゴン』の面影がまだ残っているような気がするんです。私がやめたら、市場の息づかいがまたひとつ消えてしまうでしょう」。
バンコー市場は100年以上の歴史を持ち、その名の通り「碁盤の目(バンコー=ban co)」のような配置で知られている。路地が入り組み、まるで迷路のような市場に足を踏み入れると、人々はひしめき合う屋台の中に、ここにしかない暮らしのリズムと記憶の空間を感じる。




)

 免責事項
免責事項

)
)
)
)
)
)
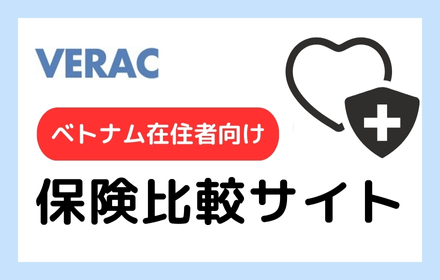
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)