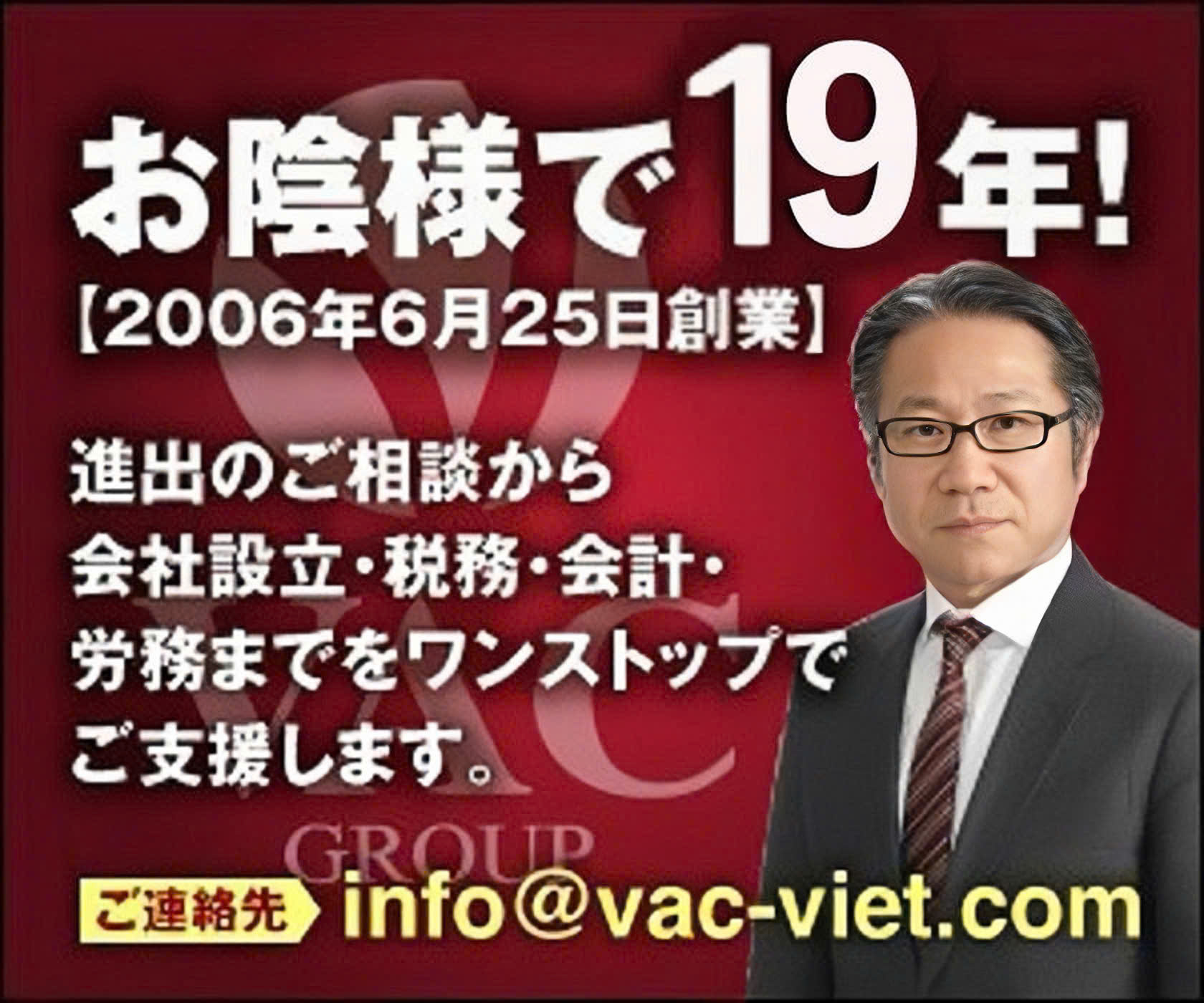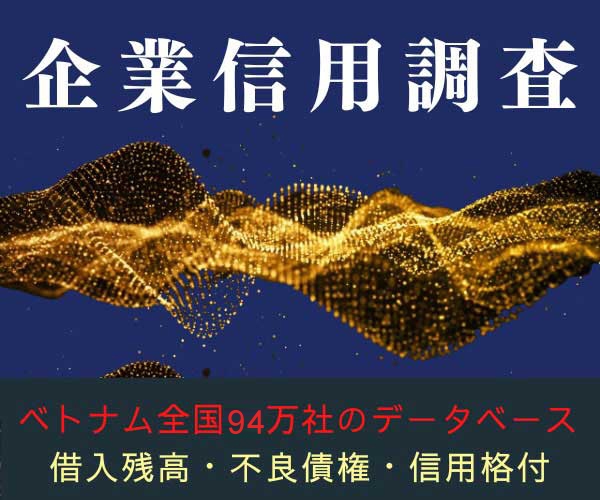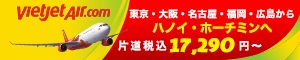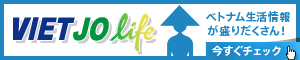サイゴンに生まれアメリカで育ち、アフリカで研究生活を送るベトナム系米国人女性グエン・ティエン・ガー。彼女の名前「ティエン・ガー」は白鳥を意味するが、文字通り彼女は鳥のように世界を飛びまわっている。
ガーは1976年生まれ、彼女が生まれて間もなく父親は家族を捨てて出ていってしまったため、父親の顔も知らない。1982年、母親や親せきとともにベトナムを離れるが、暮らし向きは決して楽ではなく、そのことが彼女を勉強に駆り立てていった。そしてニューヨークの名門校バーナード大学に入学する。
「霊長類の研究をしようと思ったのはいつから?」との問いに、ガーこう答えた。「子どものころ、動物や原始人について研究する科学者はお金がもらえるということを何かの本で読んだの。探検家や科学者の本を読んでいくうち、私も彼らが足を踏み入れた地を見てみたいと思ったんです。その唯一の方法は、勉強して研究者になることだと知りました」。
大学ではマリナ・コーズ教授のクラスで霊長類学を学んだ。そのときコーズ教授はケニアの森林に生息するミドリザルを研究していた。「200人近いクラスメートの中からケニア行きの助手に選ばれるためには、飛び抜けた能力を証明しなければなりませんでした。私は申請し、合格しました」。1997年6月、ガーはケニアに向かった。彼女にとって初めてのアフリカ探検だった。
彼女は6人の助手のうちの1人。家を遠く離れ全く異なる環境での生活は、エキサイティングでもあり試練でもあった。その旅で彼女はピーター・フェイシングと出会う。彼もまた助手の1人だった。自然への愛と研究への熱意を同じくする2人は次第にひかれあい、恋に落ちる。2人は後に夫婦となる。
ガーは博士課程の研究で、2002年7月から2003年11月までケニア南部のアンボセリに滞在した。ここはライオンやゾウなど多くの野生動物が生息する場所で、昼間の気温は40度以上になる。毎日ケニア人のスタッフと車でサルの生息地に向かい、サルの行動を観察し、糞を持ち帰って分析した。
アンボセリでの暮らしは何もかもが違っていた。首都ナイロビに行くのは2、3カ月に1回で、最も近い町に出るのにも車で何時間もかかる。「そのときは本当に家や夫やベトナム料理が懐かしくてたまらなかったわ」。時にホームシックにかかるものの、じゃれあっているサルやキリマンジャロの姿を眺めていると、心が晴れて再び研究への意欲がわいてきたという。
ガー夫妻は2005年、エチオピアの標高3000メートルの高地でゲラダヒヒの研究を開始する。毎日ヒヒの群れを徒歩で追う、文明とはかけ離れた生活が続く。困難ではあるが2人は研究に没頭している。最近彼女は、彼らのしぐさの意味を理解し、個体の顔を見分けられるようになったという。これで研究にのめりこむ理由がまた増えた。

 から
から




)
)

)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)